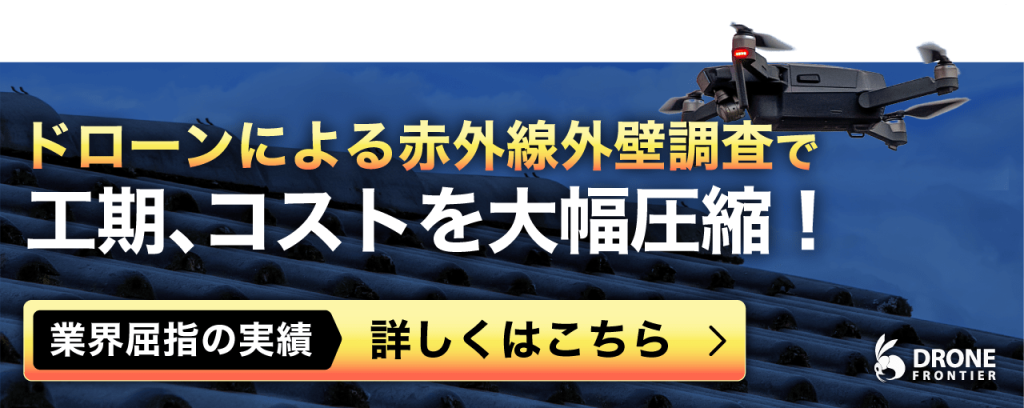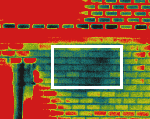2021年末時点での全国のストックマンションは約685.9万戸となっています。そのうち築40年を超えるマンションは115.6万戸に上り、総数の約17%を占めています。
しかし、これら経年劣化が進むマンション・ビルの多くの外壁はタイルで構成されているため、劣化が放置されると剥落し、最悪の場合、人身事故を引き起こす可能性があります。実際に毎年、タイル剥落による事故が報告されています。
ストックマンション数は今後10年で約2.2倍、20年で約3.7倍に増加すると予測されています。築年数経過のマンションに対する適切なメンテナンスが喫緊の課題となっているのです。
タイル剥落による事故

マンションオーナーたちの中には、外壁タイルはメンテナンスが必要ないとお考えの方もいらっしゃいますが、マンションタイルの劣化による落下事故のリスクがあり危険です。
タイルの落下事故は毎年発生し、過去には落下したタイルが人にあたり死亡事故に至った事例や、強風により建物の高さ×1.5m程度の距離までタイルが飛んだ事例もあります。敷地内だけでなく、周辺の人や車まで様々なものに被害が及ぶ恐れがあるのです。
過去、外壁タイルの剥離・落下による死亡事故での損害賠償に関して、過去最高裁での判決では、建物所有者が全面的な賠償責任を負うという判決が下りました。タイルが落下して、通行人などの第三者に負傷を負わせた場合、マンションの所有者である管理組合は建物の管理責任を問われることになるでしょう。
タイル剥落寸前!?危険な状況とは?
【危険症状】
・ひび割れ
・目次材に隙間がある
・エフロレッセンス(白華現象)
ひび割れはタイルが浮き始めている可能性が、目次材の隙間はタイルが動いている可能性があります。また、エフロレッセンスと呼ばれる白いシミのような汚れがある場合、雨水の浸透性が高くなっており、落下の原因となることもあります。
外壁タイルの剥落事故を防ぐためには、剥落する前に劣化を発見しなければいけません。
2008年の建築基準法施工規則の一部改正により、竣工後10年以上経過した建物は全面打診調査が義務付けられました。しかし、これでもなお剥落事故は発生しています。
タイルが剥落する理由
①外壁の部材は伸縮量が異なるため
外壁は、タイル・接着モルタル・コンクリートの3層から成っています。
これらの材料は外部からの温湿度変化によって伸縮しますが、それぞれ材質が異なるためその伸縮に差ができてしまうのです。
それぞれの異なった伸縮は年数が経つにつれてタイルの浮きを発生させてしまいます。
②タイルが浮いた部分に雨水が侵入するため
タイルに浮きが発生すると、その部分に雨水が侵入します。温湿度変化は日々起こるので、膨張と伸縮によってタイルの浮きが悪化し続け、結果剥離してしまうことになるのです。
外壁定期点検の義務
建築物の定期報告制度において、タイル等の外壁の仕上げの劣化状況を確認するための調査について改正され、平成20年4月1日以降、10年ごとに外壁の全面打診等調査が義務化されました。対象となるのは、タイル(湿式)仕上げ、石貼り(湿式)仕上げ、モルタル仕上げです。
調査では、特に落下により歩行者等に危害を加える可能性のある部分が対象とされています。これは外壁面の前面かつその高さの約半分の範囲で、公道や通行者の多いエリアを有するものとされています。ただし、外壁直下に強固な落下物防御施設(屋根・疵等)が設置されている場合や、植え込みにより安全が確保されている場合は除外されます。
また、全面打診等の調査方法としては、テストハンマーによる全面打診調査や赤外線調査が採用されています。これにより、ひび割れや浮き、はがれなどの劣化・損傷が見受けられた場合は、一時的な被害防止策として、バリケードやなわ張り、落下物防護ネット張り、落下防護柵の設置が必要です。
改修が必要な場合は、迅速かつ適切な対策を講じるよう呼びかけられています。
マンション・ビルの外壁タイルの点検で注目されるドローン赤外線調査

そもそも赤外線外壁調査は国に認められている
建物の老朽化を原因とする事故を未然に防ぐことを目的とし、2008年に「建築基準法第12条」に基づく「定期報告制度」が改訂されました。以降、定期的な外壁調査と報告は建物の所有者、管理人の義務となったのです。具体的には目視と手の届く範囲の打診、異常が見られた場合は外壁の全面調査が必要になるのですが、赤外線調査はこの全面調査で選定できる調査方法のひとつ。赤外線で点検した記録はエビデンスを持ったデータとして提出することができます。
赤外線外壁調査の仕組みとは?
外壁で劣化を起こした箇所と健全な箇所では表面温度に違いがみられます。赤外線はこの温度差から外壁の劣化箇所をピンポイントで特定します。たとえば外装仕上げ材のタイルが剥離(浮き)を起こしてしまった箇所は熱をこもらせていますし、水漏れを起こしている箇所は水分の蒸発時、周囲の熱を奪う特徴を持っています。赤外線調査は外壁の温度を熱画像として可視化させ、調査員が解析を行う調査方法です。
赤外線外壁調査には弱点はあるの?
赤外線外壁調査は国に認められた技術であるものの、国家資格は存在しません。ご依頼される会社の力量によって調査結果が大きく左右されます。ドローンの操作技術や知識は大前提。その上で、解析可能なデータを取る、精度の高い解析を実現することは調査員の経験に依る部分が大きいのです。また、クライアントの方と話を進める上で、最低限の建設業の知識を持っていることも調査員には求められています。弊社は全員「赤外線建物診断技能士」の資格を持った調査員が調査に当たります。
DFのタイル剥落調査
ドローン赤外線撮影と解析を内製化
ドローンを用いて赤外線外壁調査の業務を行う多くの会社は、撮影のみ自社で行い、解析を他社に委託しているケースが多いですが、弊社はドローンを用いた赤外線外壁調査の撮影から解析までの全業務を内製化しています。
内製化していることのメリットとして以下の2点が挙げられます。
①急な天候の変化に対応できるため環境要件が適した日に調査を実施し易い
②撮影班と解析班で意思の統一が図れているため、解析班が求めるデータ取得を現場で実行し易い
また、弊社では赤外線外壁調査だけでなく打診調査も承ることが可能です。そのため現場状況にあわせて最適な調査手法を選択できます。
見積もりと実際の施工費用との差が出にくい
外壁修繕では見積りと実際の施工費用に差が発生しトラブルになることがあります。
これは外壁調査の精度が低く、不具合のある箇所を見落としてしまったことが原因です。
他社の調査をもとに修繕を進めたところ、施工時に想定以上に不具合が見つかり、当初の見積もりと比べて実際の施工費用が1,000万円程高くなってしまったというケースもあります。
調査精度の高い会社に依頼をすることは、実際に施工する際のトラブル回避にも繋がります。
サービス料金:200円~480円(調査面積1㎡あたり・税別)
ドローンのみを使用した場合の調査撮影・画像分析報告書の作成にかかる料金です。調査面積によって1㎡あたりの価格が変動いたします。別途移動交通費を申し受けます。
また、ロープアクセス調査を使用する場合は1㎡あたり400〜600円(税別)、地上警備員、安全対策費、諸経費を別途申し受けます。
詳しくはこちらもご覧ください。